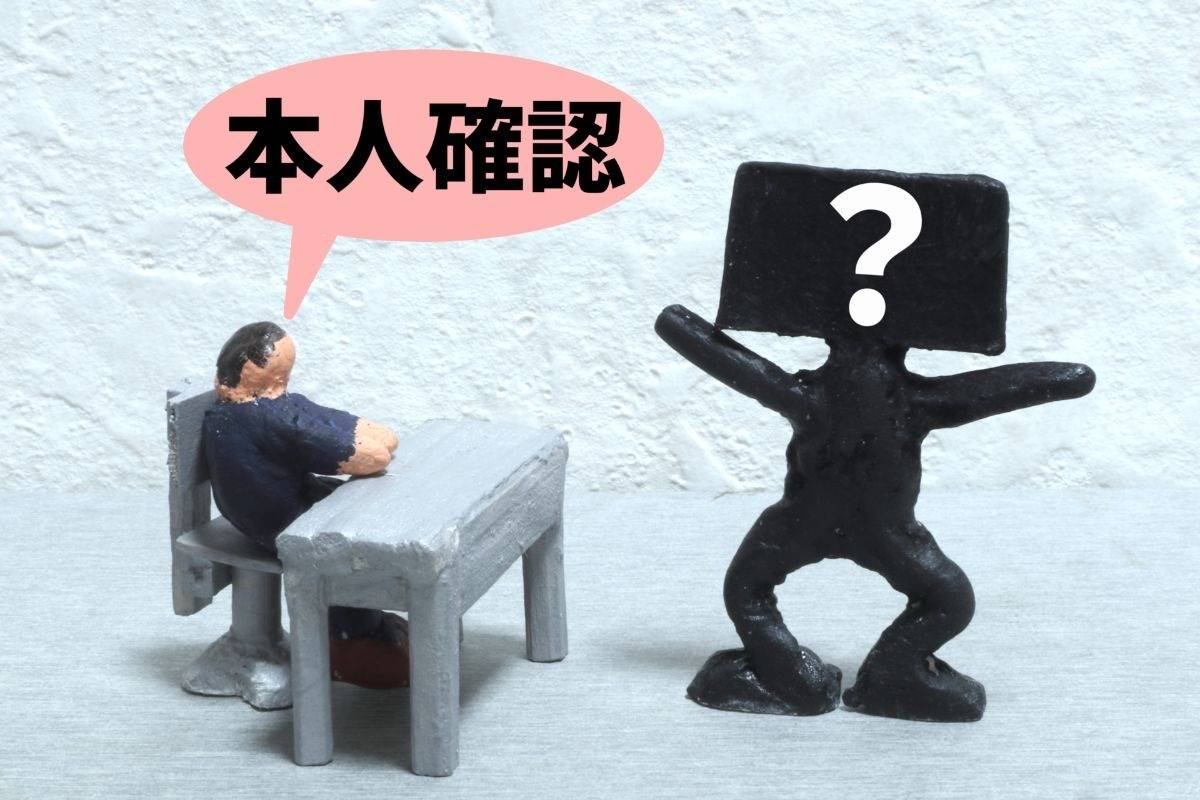不動産売却における簿価を徹底解説!高く売るための戦略と税金対策
2025/03/23
不動産を売却するとき、「簿価」について正しく理解していますか?
「購入時よりも価値が上がったか下がったか、売却益はどれくらい出るのか…」このような疑問や不安を抱えている方は少なくありません。特に、法人と個人では簿価の扱いが異なるため、税金や会計処理に影響を与える可能性があります。
例えば、簿価が低い物件を売却すると、売却益が大きくなり、その分税負担も増加することがあります。一方で、簿価が高い場合は、減価償却の影響で思ったよりも利益が出ないことも。売却を成功させるには、これらのポイントを正しく理解し、最適なタイミングと方法で取引を進めることが重要です。
この記事では、不動産売却時における簿価の基本から、法人・個人の違い、税金対策まで詳しく解説します。適切な知識を身につけることで、余計な税負担を避けながら、最大限の利益を確保するための戦略が見えてきます。
知らないまま進めると、思わぬ損失につながることもあります。ぜひ最後まで読んで、あなたにとって最適な不動産売却の方法を見つけてください。
株式会社リブレクトは、不動産売却を専門にサポートするエージェントです。売主様の利益を最大化するため、魅力的な販売資料の作成や広範な情報発信を行い、多くの購入希望者にアプローチします。また、築年数が経過した物件でもリフォームや再建築のプランを提案し、価値を引き出します。高値売却・費用節約・早期売却の3つのプランをご用意し、お客様に最適な売却方法をご提案いたします。不動産売却なら、株式会社リブレクトにお任せください。

| 株式会社リブレクト | |
|---|---|
| 住所 | 〒176-0005東京都練馬区旭丘2丁目45−2 山喜ビル 5F |
| 電話 | 03-5926-7528 |
目次
不動産売却と簿価の基本概念
簿価とは?定義と仕組み
不動産売却における簿価とは、財務会計上の帳簿に記載されている不動産の価値を指します。これは購入時の取得価額から、減価償却などを反映させた後の価格となり、売却時の損益計算において重要な役割を果たします。
簿価の基本構造は以下の通りです。
- 取得価額: 不動産を購入した際の価格に、仲介手数料や登記費用を加えたもの。
- 減価償却: 建物に適用され、耐用年数に応じて徐々に簿価が減少。
- 資本的支出: 修繕や改築など、価値を向上させる支出がある場合は簿価に加算。
- 売却時の評価: 売却時点での簿価と実際の売却価格の差が、譲渡所得として計算される。
土地には減価償却が適用されず、取得時の価格がそのまま簿価として扱われます。これに対し、建物は経年によって価値が減少し、簿価も低下します。
簿価の理解が必要となるケースには以下のようなものがあります。
- 法人や個人事業主が決算時に資産評価を行う場合
- 不動産売却時に課税対象となる譲渡所得を計算する場合
- 相続や贈与で不動産を受け継いだ際に簿価を把握する必要がある場合
簿価は税務処理や売却戦略の判断において極めて重要な指標であり、適切な管理が求められます。
簿価と時価の違いを理解する
簿価と時価は混同されがちですが、それぞれ異なる概念です。簿価は財務会計上の価値であり、過去の取得価格を基準に計算されます。一方で、時価は市場における現在の取引価格を示します。
違いを整理すると、以下のようになります。
| 項目 | 簿価 | 時価 |
| 基準 | 購入時の取得価格 | 現在の市場価格 |
| 変動要因 | 減価償却や資本的支出 | 需給バランス、経済状況 |
| 影響を受ける要素 | 会計処理、税務計算 | 不動産市場、景気動向 |
| 適用範囲 | 決算、税務申告、損益計算 | 売却時の価格決定 |
例えば、購入当時に3,000万円だった建物の簿価が、10年後に減価償却によって1,500万円まで減少したとします。しかし、市場の地価上昇などにより、同じ不動産の時価が5,000万円に達していることもあり得ます。
この差があることで、不動産売却時には以下のような影響が出ます。
- 簿価よりも高い価格で売却した場合: 売却益が生じ、譲渡所得税が発生。
- 簿価よりも低い価格で売却した場合: 損失として計上できる可能性がある。
法人や個人が不動産売却を考える際には、簿価と時価の違いを理解し、どのタイミングで売却するのが有利かを検討する必要があります。
簿価が不動産売却価格に与える影響
簿価は売却価格の決定に直接影響を与えるものではありませんが、売却時の税金や損益計算に大きな影響を及ぼします。不動産売却を検討する際、以下の点を考慮することが重要です。
- 譲渡所得の計算 売却価格から簿価を差し引いた額が譲渡所得となり、課税対象になります。簿価が低いほど、売却益が大きくなり、税額も増加する可能性があります。
- 減価償却が適用される建物 建物の簿価は耐用年数に応じて低下します。例えば、築20年以上の物件では簿価がほぼゼロに近づくこともあり、売却益がそのまま課税対象になることがあります。
- 土地の簿価は変動しにくい 土地には減価償却が適用されず、基本的に取得時の価格が維持されます。しかし、再評価が行われると簿価が変動することもあります。
- 税務対策としての活用 簿価が低くなったタイミングで売却することで、譲渡所得を最小限に抑えることが可能です。逆に、売却前に資本的支出を行うことで簿価を引き上げ、税額を調整することもできます。
簿価が売却価格そのものを決めるわけではありませんが、税務計算に大きく関わるため、適切な管理と計画が求められます。
法人・個人で異なる簿価の扱い
簿価の取り扱いは法人と個人で異なります。それぞれの違いを整理すると、以下のようになります。
| 項目 | 法人 | 個人 |
| 簿価の計算 | 減価償却を経理処理 | 確定申告時に適用 |
| 会計基準 | 企業会計基準に準拠 | 所得税法に基づく計算 |
| 税務処理 | 法人税が適用 | 譲渡所得税が適用 |
| 損益の扱い | 売却損益を経費処理可能 | 売却益は譲渡所得税の対象 |
法人の場合、不動産は事業用資産として扱われ、減価償却費を経費として計上できます。そのため、長期間所有することで簿価が大きく減少し、売却時の利益が大きくなる可能性があります。
一方、個人の場合は、不動産の売却による利益が譲渡所得として課税されます。特に、所有期間が5年を超えると税率が低くなるため、売却時期の選定が重要になります。
また、法人と個人で異なるのは、税務上の優遇措置です。
- 法人のケース
- 減価償却費を経費として計上可能
- 売却損が生じた場合、他の事業収益と相殺可能
- 資産管理会社を設立することで、節税の選択肢が広がる
- 個人のケース
- 3,000万円の特別控除が適用される可能性がある
- 居住用不動産の場合、所有期間による税率優遇措置がある
- 相続財産としての扱いによって評価額が変わる
法人・個人のいずれであっても、不動産売却を行う際には簿価を正しく理解し、最適な税務戦略を立てることが重要です。
不動産売却時に簿価を考慮する重要性
簿価が税金計算に与える影響
不動産を売却する際、税金の計算には簿価が大きく影響します。簿価とは、不動産を取得した際の価格から減価償却などを加味した帳簿上の価格のことを指します。売却価格と簿価の差額が譲渡所得となり、その額に応じて税金が発生します。
税金計算の流れは以下の通りです。
- 売却価格を確定
- 実際に売買契約を交わした価格を基準に計算します。
- 取得費の算出
- 取得費とは、不動産を購入した際にかかった金額です。
- 取得価額+購入時の諸費用(登録免許税、仲介手数料など)から、減価償却費を差し引いた額が取得費となります。
- 譲渡所得の計算
- 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用(仲介手数料など)= 譲渡所得
- 税額の決定
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下)
- 税率が高めに設定されており、所得税と住民税を合わせて約39%となります。
- 長期譲渡所得(所有期間5年超)
- 優遇税率が適用され、所得税と住民税を合わせて約20%となります。
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下)
例えば、取得費が2,000万円の不動産を3,500万円で売却した場合、譲渡所得は1,500万円となります。ここから各種控除が適用され、課税対象額が決定します。
簿価が低いほど売却益が大きくなるため、税負担も増加します。そのため、売却前に簿価の確認と節税対策を検討することが重要です。
減価償却と簿価の関係性
不動産の簿価は、減価償却によって年々減少していきます。減価償却とは、建物の価値を耐用年数に応じて徐々に減額する会計処理です。土地には適用されませんが、建物には必ず影響します。
減価償却の主なポイントは以下の通りです。
- 建物の耐用年数
- 木造住宅: 約22年
- 鉄筋コンクリート造: 約47年
- 計算方法
- 定額法: 毎年一定額を減価償却する方式
- 定率法: 初年度に大きく減価償却し、年々減額していく方式
例えば、新築の木造住宅(取得価格2,000万円)の場合、定額法で毎年約90万円程度の減価償却が発生するとします。これを10年間継続すると、簿価は約1,100万円まで減少します。この不動産を2,500万円で売却した場合、譲渡所得は1,400万円となり、税金の計算対象となります。
減価償却を考慮しないと、予想以上に税負担が大きくなる可能性があるため、売却タイミングの判断が重要です。
簿価が低い物件と高い物件の売却戦略
不動産の簿価が低いか高いかによって、売却時の戦略が異なります。
| 簿価の状態 | 特徴 | 売却戦略 |
| 簿価が低い | 減価償却が進んでおり、帳簿上の価値が小さい | 売却益が大きくなり、税負担が増える可能性がある。節税対策を検討する。 |
| 簿価が高い | 取得から間もない、または資本的支出が多い | 売却益が小さくなるため、税負担を抑えられる。長期保有を前提に売却計画を立てる。 |
簿価が低い物件は、売却益が増加するため、以下の戦略が有効です。
- 長期譲渡所得の適用を狙う
- 5年以上所有してから売却すると税率が低くなる。
- 資本的支出を増やす
- リフォームや修繕を行い、簿価を引き上げることで売却益を抑える。
- 買い手のニーズに合わせる
- 低価格帯の住宅を探している投資家向けに売却する。
一方、簿価が高い物件は、減価償却が進んでおらず、税負担を抑えられるため、売却しやすいメリットがあります。
不動産売却時の簿価評価方法
簿価の評価方法には、以下のような手法があります。
- 取得価格を基準とする方法
- 取得時の購入価格を基に計算される。
- 土地は変動しないが、建物は減価償却を適用する。
- 固定資産税評価額を基にする方法
- 市区町村が決定する固定資産税評価額を参考にする。
- 一般的に時価よりも低い額になることが多い。
- 時価を考慮した評価
- 周辺の不動産取引価格や市場動向を加味して評価する。
- 不動産鑑定士による評価が必要になることもある。
- 税務上の特例を活用
- 3,000万円特別控除などの税制優遇を適用することで、実質的な税負担を軽減する。
売却時には、不動産会社や税理士と相談しながら、最も有利な評価方法を選択することが大切です。
簿価の管理と適切な評価は、不動産売却時の税金対策や利益最大化に直結します。事前にしっかりと確認し、最適な売却戦略を立てることが成功の鍵となります。
不動産売却時の簿価計算方法と具体例
土地と建物の簿価の計算方法
不動産売却時の簿価を正確に把握することは、譲渡所得の計算や税務処理を適切に行うために重要です。土地と建物では、簿価の計算方法が異なります。
土地の簿価は、取得時の価格に購入時の諸費用を加えたもので、減価償却の対象にはなりません。具体的には以下のように計算されます。
土地の簿価の計算式
取得価額+登記費用+仲介手数料+不動産取得税=土地の簿価
例えば、2,000万円で購入した土地に対し、仲介手数料や登記費用などで200万円を支払った場合、その土地の簿価は2,200万円となります。売却時にはこの簿価が基準となり、譲渡所得が算出されます。
一方、建物の簿価は減価償却の対象となり、耐用年数に応じて毎年価値が減少していきます。
建物の簿価の計算式
取得価額−減価償却累計額=建物の簿価
例えば、新築の建物を1,500万円で購入し、法定耐用年数が30年の場合、毎年の減価償却費は50万円(1,500万円÷30年)となります。10年後には500万円が減価償却され、建物の簿価は1,000万円になります。
このように、土地は取得時の価格がそのまま簿価となるのに対し、建物は時間の経過とともに簿価が減少する点が大きな違いです。
法人の不動産売却時の簿価計算のポイント
法人が不動産を売却する際には、個人とは異なる簿価計算のポイントがあります。法人の会計では、不動産は固定資産として扱われ、減価償却費を計上しながら簿価を管理します。
法人の不動産売却における重要なポイントは以下の通りです。
- 減価償却費の適用
- 建物部分は減価償却が適用され、簿価が減少する。
- 土地には減価償却が適用されないため、取得価額がそのまま簿価となる。
- 資本的支出の取り扱い
- 建物の大規模修繕やリフォームなどは資本的支出として簿価に加算される。
- 一方、修繕費として計上される場合は費用扱いとなり、簿価には影響しない。
- 法人税との関係
- 法人が不動産を売却して得た利益(譲渡益)は、法人税の課税対象となる。
- 減価償却が進み簿価が低いと、売却時の利益が増え、法人税の負担が大きくなる。
例えば、取得価額1億円の不動産を法人が20年後に売却する場合、減価償却によって建物の簿価は大幅に減少します。その結果、売却価格と簿価の差額が大きくなり、法人税の負担が増える可能性があります。
法人の場合は、不動産の売却時期や減価償却の進行状況を考慮し、税負担を最小限に抑える売却戦略を検討することが重要です。
減価償却費を考慮した簿価の計算例
減価償却費を考慮した簿価の計算は、不動産の売却益を正しく計算するために欠かせません。具体的な計算例を見ていきます。
減価償却を考慮した建物の簿価計算例
| 項目 | 金額(円) |
| 建物取得価額 | 2,000万円 |
| 法定耐用年数 | 30年 |
| 減価償却方法 | 定額法 |
| 年間減価償却費 | 2,000万円÷30年=約67万円 |
| 経過年数 | 10年 |
| 減価償却累計額 | 67万円×10年=670万円 |
| 現在の建物簿価 | 2,000万円−670万円=1,330万円 |
この建物を3,000万円で売却した場合、譲渡所得の計算は以下のようになります。
譲渡所得の計算
売却価格3,000万円−(建物簿価1,330万円+土地簿価1,500万円)=170万円
この譲渡所得に税率が適用され、課税額が決定します。
減価償却が進むと、建物の簿価が減少し、売却益が増えるため、税負担が大きくなる点に注意が必要です。
決算書から読み取る不動産の簿価
法人が保有する不動産の簿価は、決算書の財務諸表から確認できます。具体的には、貸借対照表(バランスシート)の固定資産欄に記載されます。
決算書で確認すべき主な項目は以下の通りです。
- 固定資産の部
- 土地: 取得価額がそのまま記載される。
- 建物: 取得価額から減価償却累計額を差し引いた金額が簿価として表示される。
- 減価償却累計額
- 累積された減価償却費が記載されており、簿価の算出に必要な情報となる。
- 純資産の部
- 不動産売却益が発生した場合、利益剰余金に加算される。
決算書における不動産簿価の表示例
法人が不動産を売却する際には、決算書の数値を基に簿価と売却価格の差額を計算し、それに基づいて税務処理を行うことが求められます。たとえば、土地の取得価額が3,000万円、建物の取得価額が2,500万円で、減価償却累計額が1,000万円となる場合、建物の簿価は1,500万円となります。この簿価は、税金計算において重要な役割を果たします。
簿価を正確に把握し、適切に活用することで、売却時に発生する税金負担を最適化することができます。例えば、売却価格が簿価を上回る場合、譲渡所得が発生し、これに対して課税が行われます。しかし、簿価が低い場合には、譲渡所得が少なくなり、税金負担が軽減されます。そのため、簿価の計算方法を理解し、戦略的に売却時期や方法を選ぶことが、法人にとっては有利な取引を実現するための鍵となります。
このように、簿価の計算とその活用は不動産売却において非常に重要であり、税務処理を適切に行うことで、法人は税負担を最小限に抑え、より有利な売却を達成することができます。
不動産売却の流れと成功の秘訣
不動産売却の流れ
不動産を売却する際には、スムーズに進めるための手順を理解し、適切な準備を行うことが重要です。本記事では、不動産売却の一般的な流れと、成功のためのポイントについて詳しく解説します。
1. 売却の目的を明確にする 不動産を売却する理由によって、売却戦略が異なります。以下のような目的を明確にしましょう。
- 住み替えのため
- 資産整理や相続
- 住宅ローンの返済
- 投資目的の売却
売却の目的に応じて、適切な価格設定や販売手法を選ぶことが成功のカギとなります。
2. 不動産の相場を調べる 不動産の適正な売却価格を設定するために、周辺の相場を調査します。以下の方法で市場価格を確認できます。
- 不動産会社の査定を受ける
- 不動産ポータルサイトで類似物件の価格をチェック
- 公示地価や路線価を参考にする
売却価格が市場相場よりも高すぎると売れにくく、低すぎると損をする可能性があるため、慎重に設定しましょう。
3. 不動産会社を選ぶ 売却を依頼する不動産会社を選定します。不動産会社には以下の2つの売却方法があります。
- 仲介: 不動産会社が買主を探し、成約後に仲介手数料が発生する。
- 買取: 不動産会社が直接買い取るため、早期売却が可能。
不動産会社の実績や評判を調べ、信頼できるパートナーを選びましょう。
4. 売却価格の決定と契約の締結 不動産会社と媒介契約を結び、正式に売却活動を開始します。媒介契約には以下の種類があります。
- 専属専任媒介契約: 1社のみに売却を依頼し、自己売却は不可。
- 専任媒介契約: 1社のみに売却を依頼し、自己売却は可能。
- 一般媒介契約: 複数の不動産会社に依頼できる。
売却の希望条件に応じて、適切な契約を選びましょう。
5. 販売活動の開始 不動産会社が物件情報をインターネットや広告を通じて公開し、購入希望者を募ります。
- 不動産ポータルサイトやチラシでの告知
- オープンハウスの開催
- 不動産会社の顧客リストへの紹介
見学希望者が現れたら、内覧対応を行い、物件の魅力を伝えましょう。
6. 購入希望者との交渉 購入希望者が現れたら、価格や契約条件の交渉を行います。
- 売却価格の値引き交渉
- 契約時の手付金額の決定
- 引き渡し時期の調整
不動産会社と相談しながら、できるだけ有利な条件で契約できるよう交渉を進めましょう。
7. 売買契約の締結 交渉がまとまったら、売買契約を締結します。
- 売買契約書の作成
- 手付金の受領
- 契約内容の確認と署名
契約後のキャンセルには違約金が発生する可能性があるため、慎重に進めましょう。
8. 決済と引き渡し 売買契約が成立したら、決済と引き渡しの準備を進めます。
- 住宅ローンの残債がある場合は抵当権の抹消手続き
- 引っ越しの準備と荷物の整理
- 買主へ鍵の引き渡し
決済時には、売却代金の受領と同時に所有権移転の手続きを行います。
9. 売却後の税金と確定申告 不動産売却後には、税金の支払いが発生する場合があります。
- 譲渡所得税: 売却益に対する税金(所有期間が5年超で軽減)
- 住民税: 譲渡所得に応じた税額
- 確定申告: 翌年に売却益を申告し、必要に応じて税金を納付
特例や控除が適用される場合があるため、税理士や専門家に相談するとよいでしょう。
不動産売却は、多くの手続きが必要ですが、計画的に進めることでスムーズに取引を完了できます。売却の目的を明確にし、信頼できる不動産会社を選び、適切な価格設定を行うことが成功のポイントです。また、税務処理もしっかり確認し、売却後の負担を軽減することが重要です。
不動産売却の成功の秘訣
不動産を売却する際、多くの人々が価格面で悩み、できるだけ高い売却価格を目指します。成功した不動産売却には、単に「売る」こと以上の戦略が必要です。適切なタイミングでの売却、買い手を惹きつけるための魅力的なポイント、そして税制や市場動向を十分に考慮したアプローチが求められます。ここでは、不動産売却を成功させるための秘訣を紹介します。
1. 市場調査を徹底的に行う
不動産市場は常に変動しています。売却を検討する際、最も重要なのは市場調査です。近隣の売却価格や賃料の相場、地域の発展性や将来の価値を確認しましょう。競争の激しいエリアでは、周囲の物件と比較して差別化できるポイントを見つけることが重要です。市場が好調な時期に売却を決断することで、より高値での取引を実現できます。
2. 適切なタイミングでの売却
不動産の価格は時期によって大きく異なるため、売却のタイミングは成功の鍵を握ります。たとえば、経済が活性化している時期や低金利が続いている時は、買い手が増えるため、売却価格を高く設定できる可能性があります。逆に、経済が不安定な時期や金利が上昇している時期には、売却価格の設定が慎重になるべきです。
また、固定資産税評価額や耐用年数の変更など、税制の変動を考慮して売却タイミングを決定することも大切です。特に固定資産税評価額が改定される前に売却を行うことで、買い手の負担を軽減し、スムーズな取引が可能になります。
3. 物件の魅力を最大限に引き出す
物件の魅力を最大限に引き出すためには、リフォームやクリーニングなど、少しの手間をかけることが有効です。特に、内装や外装に手を加えることで、物件の印象が大きく変わります。小さな投資が大きな利益を生むことが多いため、買い手にとって魅力的な物件に仕上げることが重要です。
また、物件の良い点を強調し、ターゲット層に合わせた広告を行うことも成功の秘訣です。たとえば、投資家向けには収益性をアピールし、ファミリー向けには住環境や教育施設の充実度を強調することが効果的です。
4. 不動産の税務対策を理解する
不動産売却における税務は非常に重要な要素です。譲渡所得税や消費税など、売却に伴う税金を事前に把握しておくことが、売却価格の最終的な利益に大きく影響します。特に減価償却が進んだ物件や、簿価が低い物件の場合、税負担が大きくなることがありますが、税制上の特例を活用することで軽減することができます。
例えば、長期譲渡所得税の適用を受けることで税負担を抑えることができる場合があります。税理士や不動産の専門家と相談し、売却前に適切な税務対策を講じることが、成功する売却に繋がります。
5. プロフェッショナルのサポートを受ける
不動産の売却は一度きりの大きな決断であり、専門的な知識と経験が求められます。不動産エージェントや弁護士、税理士など、プロフェッショナルのサポートを受けることで、より確実な売却が実現できます。不動産エージェントは、地域市場の知識や適正価格設定のアドバイス、交渉のスキルを持っており、迅速かつ有利な取引をサポートしてくれます。
6. 柔軟な交渉術を駆使する
売却時の交渉は、最終的な価格に大きく影響を与えます。柔軟で戦略的な交渉術を用いることで、買い手と売り手双方にとって満足のいく条件を引き出すことができます。たとえば、価格だけでなく、引き渡しのタイミングや契約条件の交渉も行い、買い手にとっても魅力的な条件を提示することで、円滑に取引が進むことがあります。
不動産売却の成功には、適切なタイミング、魅力的な物件作り、そして専門家のアドバイスが重要です。市場調査をしっかり行い、売却タイミングを見極め、税務や交渉を含めた戦略的アプローチを採ることで、売却価格を最大化し、満足のいく取引を実現できます。事前にしっかり準備をして、自信を持って売却に臨むことが成功への道です。
まとめ
不動産売却における簿価の理解は、売却価格の決定や税金の計算に大きく影響を与えます。特に法人と個人では簿価の扱いが異なり、適切な知識を持たずに売却すると、思わぬ税負担が発生する可能性があります。
簿価とは、取得価格から減価償却を差し引いた帳簿上の価値を指し、売却時の譲渡所得の計算にも密接に関係します。時価との違いを理解し、最適な売却タイミングを見極めることが、無駄な税負担を避ける重要なポイントとなります。
不動産売却の際には、簿価を考慮した価格設定や税務対策が不可欠です。簿価が低い場合、売却益が大きくなり、税負担が増える可能性があります。一方で簿価が高い場合は、減価償却の影響で利益が圧縮されることもあり、事前のシミュレーションが重要です。
また、法人の場合は会計基準や税務上の処理が異なり、損益通算の活用や節税対策を講じることで、最適な売却戦略を立てることができます。個人の場合でも、譲渡所得税の軽減措置や特例を活用することで、税負担を抑えることが可能です。
不動産の売却を成功させるためには、簿価の正しい把握と、税金・会計処理に関する適切な対策が欠かせません。事前に専門家に相談し、売却時のリスクを最小限に抑えながら、最大限の利益を確保する戦略を考えることが重要です。
株式会社リブレクトは、不動産売却を専門にサポートするエージェントです。売主様の利益を最大化するため、魅力的な販売資料の作成や広範な情報発信を行い、多くの購入希望者にアプローチします。また、築年数が経過した物件でもリフォームや再建築のプランを提案し、価値を引き出します。高値売却・費用節約・早期売却の3つのプランをご用意し、お客様に最適な売却方法をご提案いたします。不動産売却なら、株式会社リブレクトにお任せください。

| 株式会社リブレクト | |
|---|---|
| 住所 | 〒176-0005東京都練馬区旭丘2丁目45−2 山喜ビル 5F |
| 電話 | 03-5926-7528 |
よくある質問
Q. 不動産売却時に簿価と時価のどちらが価格決定に影響しますか?
A. 売却価格を決定する際の基準となるのは時価です。時価は市場の動向や査定結果によって決まりますが、簿価は帳簿上の価値であり、直接売却価格には影響しません。しかし、簿価と売却価格の差額が譲渡所得税の計算に影響を与えるため、売却後の税負担を考慮する際に重要な指標となります。
Q. 不動産売却前に簿価を調整する方法はありますか?
A. 事前に簿価を調整する方法として、減価償却の見直しや税務上の特例の活用があります。例えば、耐用年数を見直すことで減価償却費の計上を調整し、簿価の変動をコントロールできます。また、法人の場合は損益通算を活用して税負担を軽減することも可能です。ただし、税務上の制約があるため、税理士などの専門家に相談することが推奨されます。
Q. 法人と個人で不動産売却時の簿価の扱いはどのように違いますか?
A. 個人の場合、不動産売却による利益は譲渡所得として課税され、所有期間によって税率が異なります。一方、法人では売却益が法人税の課税対象となり、簿価との差額が損益計算書に計上されます。また、法人では会計処理の方法や減価償却の計算方法が異なり、税務戦略によって簿価を調整しやすいメリットがあります。法人が所有する不動産の売却は税務上の影響が大きいため、事前に専門家と相談することが重要です。
会社概要
会社名・・・株式会社リブレクト
所在地・・・〒176-0005 東京都練馬区旭丘2丁目45−2 山喜ビル 5F
電話番号・・・03-5926-7528